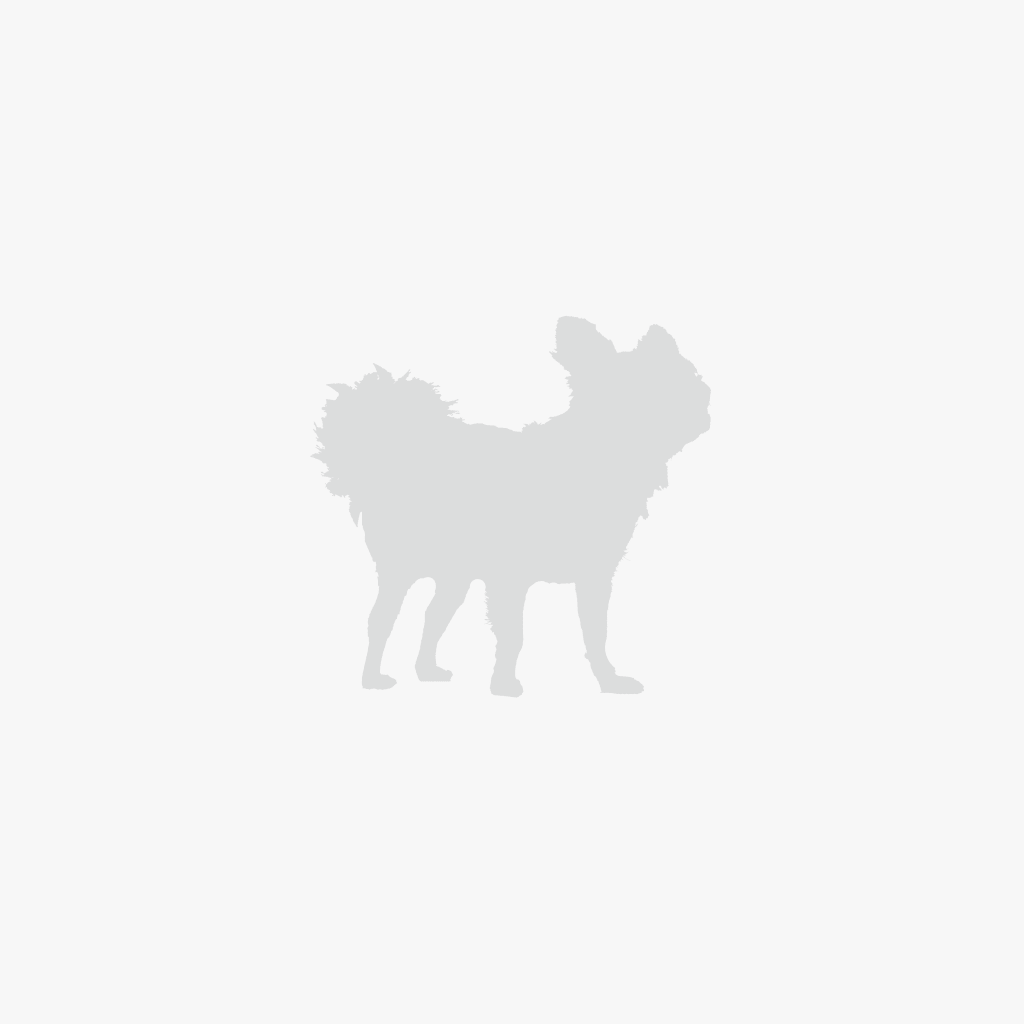QOLをなんとかする、どうにかする。STRATEGY = PR(Public Relations)× DX × Healthcare


オフィスや店舗で日々使われる「電話」。
その中でも、法人向けに特化して開発されたのが ビジネスホン(ビジネス用電話機) です。
家庭用電話と異なり、複数の外線をまとめて管理したり、内線で社員同士がスムーズに連絡を取り合えたりと、業務効率を大きく左右する仕組みが備わっています。
しかし一方で、「どのように導入すれば良いのか?」「対応年数はどのくらいか?」「コードレスは便利なのか?」「使い方は難しいのか?」といった疑問を持つ担当者も少なくありません。
本記事では、ビジネスホンの基本から、導入メリット、対応年数やコードレスの特徴、さらにはオンプレ型とクラウド型の比較までを解説します。

ビジネスホンとは、企業や団体などの法人向けに設計された多機能電話システムを指します。
一般的な家庭用電話は1回線を1台で使用する仕組みですが、ビジネスホンは 複数回線を集約し、内線・外線を柔軟に切り替えて利用できる 点が大きな特徴です。
例えば、代表番号に顧客から電話がかかってきた場合、受付が応対して担当部署に転送するといった運用が可能です。
また、社員同士で内線通話を行えば通話料は発生せず、迅速に情報共有できます。
・ 複数回線管理:外線をまとめて一括で受け、内線へ振り分け
・ 転送機能:受付から担当者へのスムーズな取り次ぎ
・ 保留・代表番号対応:顧客を待たせずに社内連携が可能
・ 会議通話:複数人で同時通話ができ、打ち合わせ効率を向上
| 項目 | 家庭用電話 | ビジネスホン |
|---|---|---|
| 回線数 | 基本1回線 | 複数回線を同時に管理可能 |
| 内線 | なし | 社員同士で無料通話 |
| 転送 | 基本不可 | 内線・外線間で転送可能 |
| 導入対象 | 個人利用 | 企業・法人利用 |
このように、ビジネスホンは 「組織の電話業務を効率化するための基盤」 といえる存在です。
特に顧客からの問い合わせが多い業種や、複数拠点を持つ法人では導入効果が大きく、業務の信頼性向上にもつながります。
ビジネスホンを導入する最大のメリットは、業務効率の向上と顧客対応力の強化です。
例えば代表番号宛に電話が入った場合、受付での一次対応から担当部署へのスムーズな転送が可能になり、顧客を待たせる時間を減らせます。また、社内連絡は内線を使うため通話料がかからず、コスト削減にもつながります。
さらに、最近ではコードレス機能やクラウド型ビジネスホンが普及しており、オフィスレイアウト変更やテレワークにも柔軟に対応できます。
これにより「場所に縛られない働き方」を実現しやすくなる点も、大きなメリットです。
主なメリットを整理すると以下の通りです。
・ 顧客対応のスピードアップ:代表番号から担当者へ即転送
・ コスト削減:内線通話は無料、通信費削減に貢献
・ 柔軟な働き方支援:コードレスやクラウド型で在宅勤務や移動中も対応可能
・ 信頼性向上:不在時も転送や留守録で対応漏れを防止
一方で、導入にはコストや運用上の注意も必要です。
まず、初期費用として端末代や配線工事費が発生します。
さらに、保守契約や修理費といったランニングコストも考慮しなければなりません。
導入時には以下のような注意点を押さえておくことが重要です。
1. 社員数・拠点数に合わせた規模設計
オーバースペックな機種を選ぶとコストが無駄になり、逆に不足すると業務に支障が出ます。
2. 通信インフラの確認
光回線やIP電話に対応しているかをチェックしないと、後から買い替えが必要になるケースもあります。
3. サポート体制の確認
保守契約の有無、故障時の駆けつけ対応、リモート保守が可能かどうかは法人にとって重要な判断材料です。
4. 社内研修やマニュアル整備
多機能ゆえに「操作が難しい」と感じる社員もいます。基本的な操作方法は導入時に共有しておくことが必要です。
ビジネスホンは一度導入すると長く使える設備ですが、対応年数の目安はおおむね7〜10年とされています。
これは本体そのものの耐久性だけでなく、部品の供給状況や通信インフラの変化にも左右されます。
・ 約7〜10年が目安
・ メーカーの部品供給終了が更新のサイン
・ 長期利用により通話品質の低下や誤動作が増える可能性
1. ISDN回線終了や光回線化
従来の通信インフラが終了すると、古いビジネスホンでは利用できなくなることがあります。
2. 修理部品の入手困難
導入から10年以上経つと、メーカー在庫がなく修理できないケースが増えます。
3. 業務の変化に対応できない
テレワークやスマホ連携など新しい働き方に対応するには、クラウド型や最新機種への更新が必要になります。
製造業のA社では、導入から12年経過したビジネスホンを使い続けていました。ある日、代表番号の外線がつながらなくなり、顧客とのやり取りが数時間ストップする事態に。部品がすでに供給終了していたため、急きょ新規導入を決定しましたが、トラブルが起きてからの更新は業務に大きな影響を与えました。
このように、「使えるうちはそのまま」ではなく、計画的な更新サイクルを意識することが法人にとって大切です。
対応年数を把握しておけば、予算計画や導入準備もスムーズに進められるでしょう。

ビジネスホンと聞くと、机の上に据え置かれた有線タイプを思い浮かべる方も多いですが、近年はコードレス型ビジネスホンの導入も進んでいます。
オフィスのレイアウト変更が多い企業や、社員が社内を移動しながら業務を行う環境では、コードレス型が強みを発揮します。
移動中でも応対可能
営業担当者や工場内のスタッフが移動しながら通話できるため、電話を取りこぼすリスクを減らせます。
固定席に縛られないので、広いオフィスや複数フロアを行き来する業務環境でも効果を発揮します。
配線不要でスッキリ
有線型に比べて配線工事が少なく、オフィスの模様替えや移転時の手間も軽減されます。
特にスタートアップや事業拡大で頻繁にレイアウトを変更する企業に向いています。
フレキシブルな働き方に対応
昨今の働き方改革では「固定席を持たないフリーアドレス制」を採用する企業も増えています。
コードレス型を導入すれば、どこに座っても同じ番号で通話でき、テレワークやサテライトオフィスとの相性も良好です。
電波干渉により通話が不安定になることがある
Wi-Fiや電子レンジなどの電波と干渉することで、音声が途切れたり雑音が入る場合があります。
オフィス内の電波環境を事前に確認しておくことが重要です。
子機の同時利用台数に制限がある
コードレス子機は無制限に増やせるわけではなく、同時接続数に上限があります。
社員数が多い場合は、有線型やクラウド型との組み合わせを検討した方が効率的です。
バッテリーの寿命がある
子機は充電池で稼働するため、数年に一度は交換が必要です。
長時間の連続通話を多用する部署では、有線型と併用して安定性を確保する運用が望まれます。
ビジネスホンは多機能ですが、基本的な操作に慣れてしまえば日常業務で大きな力を発揮します。
導入時には社員に対して操作方法を周知しておくことで、顧客対応の品質を一定に保つことができます。
・ 内線・外線の使い分け
社内連絡は内線で行えば通話料はかかりません。外部とのやり取りは外線を使い、必要に応じて代表番号からの着信を担当部署に転送できます。
・ 保留・転送
顧客からの電話を一時的に保留し、担当者へ転送する機能です。保留音を流すことで「放置されている」という印象を避けられ、安心感を与えられます。
・ 会議通話(多者通話)
複数人で同時に会話が可能です。出張中の社員や別拠点をつなぎ、迅速な意思決定に役立ちます。
・ 留守録・音声ガイダンス
営業時間外や不在時に顧客のメッセージを残してもらえる機能。最近ではIVR(自動音声応答)を活用して、問い合わせ内容ごとに担当部署へ直接つなぐ仕組みを導入する企業も増えています。

・ 不動産業
代表番号に入った電話を受付が受け、物件担当者へ内線転送。担当者が外出中でもコードレス子機で対応でき、顧客を待たせません。
・ コールセンター
着信を複数のオペレーターで分担し、混雑時には自動で保留音を流す仕組みを導入。対応漏れを防ぎ、顧客満足度を維持。
・ 中小企業の営業部門
外出が多い営業担当者が、事務所内の誰かに一次対応してもらい、その後コードレス子機やクラウド型システムで直接フォロー。取引機会を逃さずに済みます。
・ 医療機関(クリニックや病院)
受付での問い合わせ(予約変更・診療内容の確認など)を、内線で看護師や担当医にスムーズに転送可能。待合室の混雑を避け、患者対応を効率化できます。
・ 製造業(工場や倉庫)
現場作業員がコードレス子機を持ち歩くことで、管理事務所からの連絡を即座に受け取れる体制を構築。緊急時の対応や作業指示のスピードが格段に向上します。
ビジネスホンは従来の「オンプレ型(社内設置型PBX)」と、近年注目される「クラウド型(IP電話サービス)」に大別されます。
それぞれの特性を理解することで、自社に合った導入方法を選びやすくなります。
オンプレ型は社内に専用装置(PBX)を設置し、そこに電話機を接続して運用する仕組みです。
安定性やセキュリティ面で優れており、外部の通信環境に依存しないため、金融機関や官公庁など厳格な管理が求められる組織で長く採用されてきました。
ただし、拠点追加や人員増加の際には配線工事や機器増設が必要となり、柔軟性には欠ける面があります。
クラウド型はインターネットを介して提供されるサービスで、スマホやPCからも利用できる点が強みです。
拠点追加はIDを増やすだけで対応でき、テレワークや外出先からの利用にも最適です。
初期費用を抑えられる一方、安定した通信環境がなければ音質が不安定になることもあるため、導入前にインターネット環境を見直す必要があります。
| 項目 | オンプレ型(従来型PBX) | クラウド型(IP電話) |
|---|---|---|
| 設置 | 社内に専用装置を設置 | インターネット経由で利用 |
| 初期費用 | 高い(機器購入・工事費) | 低い(月額課金が中心) |
| 拡張性 | 拠点追加に工事が必要 | ID追加で柔軟に拡張 |
| 保守 | 自社または保守契約が必要 | ベンダー側が保守対応 |
| テレワーク対応 | 不向き(社内利用が中心) | スマホ・PCから利用可能 |

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、ビジネスホンも「単なる電話機」から「情報活用のプラットフォーム」へと進化しています。
従来の通話機能に加え、クラウドやAIとの連携によって、業務効率化や顧客満足度の向上を後押しするツールとなりつつあります。
クラウド型ビジネスホンは、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援ツール)と組み合わせることで、通話履歴を顧客データと自動で紐づけられます。
これにより「誰が、いつ、どの顧客と話したのか」が一目で分かり、営業活動の可視化や顧客対応の標準化が可能になります。
AIを活用した音声認識や解析技術も普及しています。
例えば、通話内容を自動でテキスト化して議事録を作成したり、顧客の感情を分析してオペレーターにリアルタイムでフィードバックしたりすることが可能です。
人手不足の中でも、質の高い顧客対応を実現できる点が注目されています。
クラウド型やアプリ型のビジネスホンを導入すれば、社員は自宅や外出先からでも自社の代表番号で発着信できます。
これにより、オフィスに縛られずに顧客対応が可能となり、柔軟な働き方を支えるインフラとしても活躍します。
今後は「電話=音声通話」にとどまらず、チャットやビデオ会議、社内グループウェアとシームレスに統合される方向性が進むでしょう。
ビジネスホンはDX推進の一部として、コミュニケーション基盤を支える存在になりつつあります。
ビジネスホンは、単なる「電話機」ではなく、法人にとって 顧客対応力を高め、社内の情報共有をスムーズにするための基盤 といえる存在です。導入の際は以下のポイントを押さえておくと安心です。
・ 導入の目的を明確にする:顧客対応の効率化か、テレワーク対応か、目的に応じて最適な機種を選定
・ 対応年数を意識する:おおむね7〜10年を目安に更新を検討し、トラブルを未然に防止
・ 有線型かコードレス型かを比較する:固定席中心か、社内移動が多いかで選択肢が変わる
・ オンプレ型かクラウド型かを検討する:安定性重視か、柔軟性・低コスト重視かで最適解を選ぶ
近年はクラウドやAIの発展により、ビジネスホンはDXの一翼を担うツールへと進化しています。 自社の規模・業種・働き方に合わせて最適なシステムを導入することで、業務効率だけでなく、顧客満足度の向上や企業の信頼性向上にもつながるでしょう。
テリーナテリーナではビジネスホンを取り扱っております。
お困りごとやご質問などありましたら、お問い合わせよりご気軽にご相談ください。