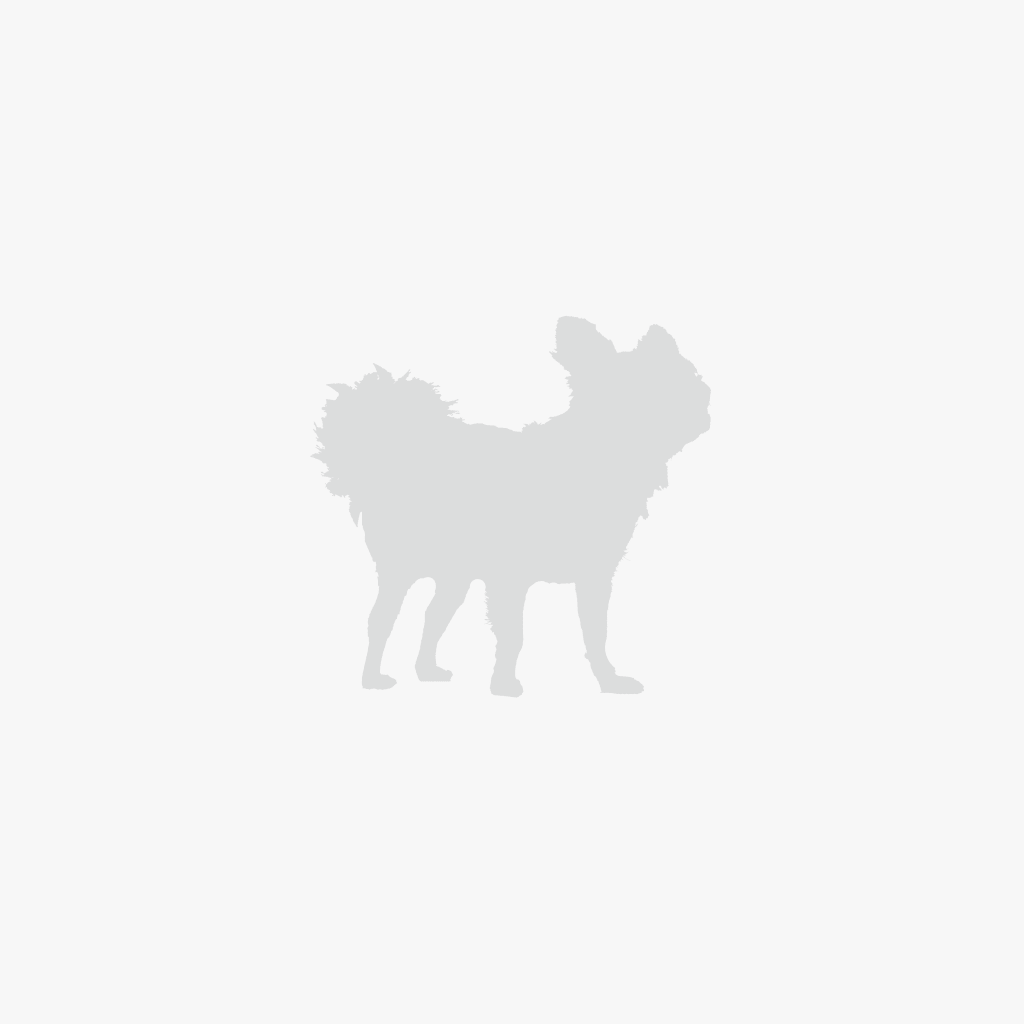QOLをなんとかする、どうにかする。STRATEGY = PR(Public Relations)× DX × Healthcare


玄関のカギを閉めたかどうか、毎朝出勤時や閉店後に気になったことはありませんか?
また、社員やスタッフの入退室をもっと効率的に管理したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
そんな悩みを解決してくれるのが「電気錠」です。
電気錠は、鍵を物理的に差し込まなくても、ICカードや暗証番号、スマホなどで簡単に施錠・解錠ができる防犯設備です。
最近では、オフィスや店舗はもちろん、集合住宅や賃貸物件、さらには個人の住宅でも導入が進んでおり、利便性と防犯性を両立できる新しい鍵のカタチとして注目されています。
とはいえ、「電気錠ってそもそもどんな仕組みなの?」「今のドアにも後付けできるの?」「費用はどのくらいかかるの?」といった疑問や不安を持つ方も多いでしょう。
本記事では、そんな方のために、電気錠の基礎知識から、仕組み・種類・後付け設置の方法、そしておすすめの設置場所や活用アイデアまでをわかりやすく解説します。

電気錠とは、電気の力でカギの開け閉めを行う防犯設備です。
近年では、オフィスや店舗、住宅でも導入が進んでおり、鍵を物理的に差し込まなくてもボタン操作やICカード、スマートフォンで施錠・解錠できるタイプも増えています。
ここでは、そんな電気錠の基本的な構造や仕組み、そしてどのようなシーンで使われているのかを、初めての方にもわかりやすくご紹介します。
電気錠とは、電気の信号によって錠を開閉する装置のことです。
従来のカギ(物理錠)は、鍵穴に差し込んで手動で回す必要がありますが、電気錠はボタン、カードリーダー、暗証番号などによって自動で動作します。
また、電気錠はドアの内側に電気的なロック機構が備わっており、解錠信号がない限り施錠状態を保ちます。
このため、電気錠はセキュリティの強化や利便性の向上を目的として、さまざまな施設で活用されています。
なお、似た言葉に「電子錠」がありますが、これは主に電池で動作する簡易タイプを指すことが多く、電気錠よりも構造がシンプルで、家庭用として普及しています。
業務用としての信頼性や拡張性を重視するなら、電気錠の方が適している場合が多いです。
電気錠は主に以下のようなパーツで構成されています。
| 部品名 | 説明 |
|---|---|
| ロック本体(錠前) | 扉内部に設置されるメイン部分。 |
| 制御機器 | 開閉の信号を送るリモコン・ICリーダー・センサーなど。 |
| 電源部 | 乾電池またはAC電源が用いられます。 |
仕組みとしては、外部からの入力(ICカードをかざす・暗証番号を入力するなど)で「解錠」の信号が送られると、電気的に錠前が解除されドアが開くようになります。通常時は「施錠」状態を保ち、信号が届かない限り開きません。
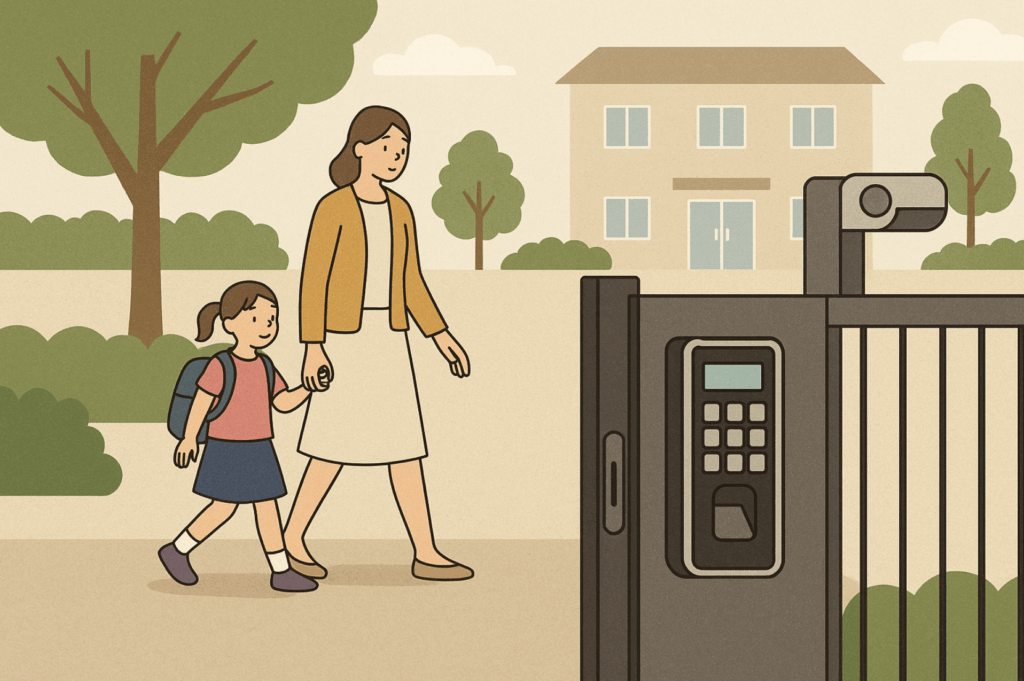
電気錠は、物理的な鍵の管理に比べて利便性が高く、防犯性も向上することから、法人・個人問わず導入が広がっています。
・ オフィスビル・工場の出入口管理
社員証やICカードによる入退室管理がしやすく、セキュリティ強化にも有効です。
・ 店舗の裏口・倉庫
鍵の持ち回りが不要で、閉め忘れ防止機能や自動施錠機能も備えているため、業務効率が向上します。
・ 集合住宅・賃貸物件
共用エントランスや各戸の玄関に設置されることで、鍵の紛失や複製のリスクを減らせます。
・ 保育園・学校・医療施設など
外部からの無断侵入を防ぐ目的で活用され、安全管理の一環として導入されるケースが増えています。
・ 宿泊施設(ビジネスホテル・民泊)
宿泊者がICカードや暗証番号で入室できる電気錠は、無人チェックインにも対応でき、運営効率が上がります。
・ 自宅やセカンドハウス
スマホ連携によって離れた場所からでも開け閉めが可能で、防犯と利便性の両立が可能です。
電気錠と一口にいっても、その種類や仕組みにはさまざまなバリエーションがあります。
取り付けるドアの種類や使用する目的によって、適した製品は異なります。
ここでは、電気錠の代表的な種類や動作方式の違い、そして法人や店舗、住宅など目的別にどのタイプが向いているのかを、分かりやすく解説していきます。
電気錠は、取り付ける扉の種類によって対応できる製品が異なります。
取り付け位置や建物の構造によって選択肢が変わるため、現地確認や専門業者への相談が必要です。
以下は主な例です。
・ 開き戸用電気錠
住宅やオフィスなどで一般的。内開き・外開きの向きも考慮して選ぶ必要があります。
・ 引き戸用電気錠
和風建築や店舗などで多く見られる引き戸にも対応する製品が登場しています。
・ 自動ドア対応型
商業施設や病院などに設置されている自動ドアに対応した、電気制御の特殊タイプです。
電気錠には主に以下のような動作方式があります。
| タイプ | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 電池式 | 乾電池で動作 | 配線工事が不要・後付けしやすい | 電池切れに注意 |
| 電源式 | AC電源を使用 | 長時間の安定動作・法人向けに多い | 電気工事が必要 |
| スマート連携型 | スマホやクラウドで操作 | 遠隔管理・多機能性が高い | ネット環境の安定が必要 |
電気錠は使う場所によって最適なタイプが異なります。
以下のように、導入シーンごとに適したモデルを選ぶのがポイントです。
使用環境や目的に応じて最適な電気錠を選ぶことで、防犯性だけでなく運用のしやすさや利便性も向上します。
・ 法人オフィス・工場
社員証やICカード対応の電源式タイプが主流。
勤怠管理システムとの連携や、複数拠点での一元管理にも対応できます。
・ 小売店舗・倉庫
電池式や暗証番号式の電気錠が便利。従業員の出入りが多い場所では、自動施錠機能付きがおすすめです。
・ 賃貸住宅・一般家庭
スマートロック型の電池式モデルが人気。
鍵の受け渡しが不要になるため、民泊でも活用されています。
・ 医療機関・介護施設
関係者以外の立ち入りを防ぐ目的で、非接触ICカードや顔認証対応の高機能モデルが採用されています。
・ 保育園・学校・教育施設
セキュリティ強化のために、オートロック+職員証連携型を導入するケースが増加中。
親の送迎時にも安心感があります。
・ 無人オフィス・レンタルスペース
スマホアプリやクラウド管理対応モデルで、ユーザーごとにアクセス制限を設定でき、鍵の受け渡し不要で効率的です。

電気錠を導入したいと考えていても、「今あるドアに後付けできるの?」といった不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、電気錠の後付けが可能な条件や施工方法などのポイントについてわかりやすく解説します。
電気錠を後付けできるかどうかは、ドアの素材・構造・厚さ・開閉方式によって判断されます。
特に注意が必要なのは以下の点です。
・ ドアが木製か金属製か(取り付けネジや電磁部品の固定に影響)
・ ドアの厚みが適合範囲にあるか(一般的には30~50mmが標準)
・ 引き戸・開き戸などの開閉方式(製品ごとに対応可否が異なる)
また、賃貸物件の場合はオーナーや管理会社への事前確認が必要です。
最近では「工事不要・貼り付け式」のスマートロックも登場しており、ドアの形状に合えば自分で簡単に後付けできるタイプもあります。
後付け電気錠の施工方法は、製品によって大きく異なります。
導入前には、対象のドアや建物の構造に適した製品選びと、施工の難易度を確認しておくことが重要です。
・ 電池式スマートロックの場合
貼り付け・ネジ止めのみで施工可能。施工時間は30分〜1時間程度。
・ 電源式電気錠の場合
ドアや壁への穴あけ、電源配線工事が必要になるため、専門業者による施工が前提。所要時間は数時間〜半日ほど。
・ 制御装置・インターホン連動型など複雑な機器
施設全体のシステムと連携する場合は、設計段階からの調整が必要で、施工には1〜2日かかることもあります。
電気錠はただ取り付けるだけでなく、「どこに設置するか」や「どう活用するか」でその効果が大きく変わります。
玄関や裏口などのセキュリティ強化はもちろん、業務効率化や社員の安全管理にもつながるケースも多くあります。
ここでは、電気錠を効果的に使うための設置場所と、他の防犯設備と連携させる運用アイデアを紹介します。
電気錠の設置場所として代表的なのが、以下のような出入口です。
場所に応じた鍵の種類(暗証番号、ICカード、スマホ連携など)を選ぶことで、利便性と防犯性を両立できます。
・ 建物の正面玄関
営業時間外の侵入を防ぐとともに、誰が入ったかを記録する仕組みを加えればセキュリティが大幅に向上します。
・ 裏口・勝手口・搬入口
人目につきにくい場所こそ不審者の侵入口になりやすく、電気錠の自動施錠機能で締め忘れリスクも回避できます。
・ 社内事務所の個室扉
重要書類や機密情報を保管するスペースのセキュリティ強化にも有効です。
電気錠は単体でも防犯性がありますが、他の設備と組み合わせることでさらに効果を高められます。
これらの連携を通じて、防犯性を高めるだけでなく、利用者の手間やストレスを軽減することも可能です。
・ 防犯カメラと連携
解錠時に録画を開始したり、不正アクセス時に警告通知を出すなど、状況を把握しやすくなります。
・ インターホン・モニターと連携
来訪者の顔を確認してから解錠できるため、無人受付や店舗でも安全です。
・ オートロック設定
ドアが閉まると自動で施錠されるため、締め忘れの心配がなく、夜間や休業時の不正侵入を防ぎます。
電気錠は、防犯目的だけでなく出入り管理や業務効率化の面でも効果を発揮します。
・ 社員証やICカードで入退室を記録
いつ誰が出入りしたかを自動で記録でき、勤怠管理やトラブル時の確認に役立ちます。
・ クラウド型勤怠システムと連携
電気錠の解錠が出勤の記録として反映されるなど、人事・労務の省力化が図れます。
・ エリア制限管理
部署ごとにアクセス権を設定し、関係者以外が入れないエリアを作ることで、情報漏えいや事故を未然に防ぎます。

電気錠の導入を検討する際は、以下のようなチェック項目を押さえておくと安心です。
・ ドアのタイプ・材質・開閉方式は電気錠に適合しているか?
・ 使用目的は何か?(防犯、入退室管理、鍵の共有回避など)
・ 希望する操作方法(ICカード、暗証番号、スマホ連携など)
・ 電源の確保が可能か?(電池式/電源式)
・ 後付け可能かどうか? DIYで設置可能か、業者が必要か
・ 予算とランニングコストは想定内に収まるか?
・ 複数拠点での利用やシステム連携の必要性はあるか?
これらの項目を事前に整理しておくことで、導入後のトラブルや後悔を防ぐことができます。
電気錠の基本から仕組み、後付け設置やおすすめの設置場所・活用方法まで幅広くご紹介してきました。
電気錠は防犯性だけでなく、利便性や業務効率化にもつながる優れた設備です。
とはいえ、設置環境や使用目的によって適切なタイプは異なります。
導入の際には、いくつかのポイントを確認しながら、信頼できる製品とサポート体制を持つ業者を選ぶことが成功のカギになります。
初めての電気錠導入で不安がある場合は、まずは無料見積や相談を活用するところから始めてみてはいかがでしょうか。
テリーナテリーナでも電気錠を取り扱っております。
お困りごとやご質問などありましたら、お問い合わせよりご気軽にご相談ください。